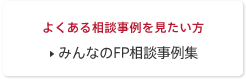バックナンバー
民間医療保険への加入検討前に公的制度について知ろう
「日本人は保険好き」とよく言われるとおり、まだ保険に加入していないからという理由で民間の医療保険への加入を検討する人も見かけます。今回は、民間の医療保険への加入を検討する前に、お金の面から知っておくとよい公的医療保険制度などについて解説します。
健康保険とは
国民皆保険の下、健康保険に加入している人は、保険適用の医療費に対する自己負担割合が原則6歳(就学)以上70歳未満で3割、それ以外の年齢では収入などに応じて1~3割のいずれかになります。すなわち、保険が適用される診療については、健康保険によって7割以上の医療費をカバーできます。一方で、自由診療など保険が適用されない医療費については、全額自己負担となります。
高額療養費制度の仕組み
健康保険が適用されて自己負担額が軽減された場合でも、通院や入院が長引くと自己負担額は高額になり得ます。そのような場合の自己負担軽減のために「高額療養費制度」が設けられています。高額療養費制度では、月ごとに医療費の自己負担額の上限が定められており、それを超える場合には後から超えた分が払い戻されます(事前に限度額適用認定証の交付を受けている場合は、医療費の支払い時に提示することで自己負担限度額を超える分を支払う必要はなくなります)。
この医療費の自己負担額の上限は、年齢や収入によって決められており、年収約370万円までの場合には最高でも57,600円、年収約370万円以上の場合には医療費に比例した金額となります。
例えば、年収約370万円~約770万円の70歳未満の方で、100万円の医療費が発生して自己負担(3割)が30万円かかる場合でも、実際に支払う医療費の上限は87,430円となります。
※上記例の自己負担額の上限:80,100円+(医療費100万円-267,000円)×1%=87,430円
※高額療養費:300,000円(3割)-87,430円(自己負担額上限)=212,570円
高額療養費制度における医療費の自己負担額の上限は月ごとに適用されるため、月が変わるとまた上限まで自己負担が発生するものの、過去12カ月以内に3回以上、上限額に達している場合には、4回目から「多数回」該当となり、上記の例では上限額が44,400円に下がります。
医療費控除の活用
医療費控除を希望する年の1月1日から12月31日までの間に、自身及び生計をともにする家族のために実際に支払った医療費の合計額から保険金などで補てんされる金額を引いた額が10万円(その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等の5%の額)を超える場合、確定申告を行うことで、その超えた額の所得控除を受けることができます。
この税制メリットは、その超えた額がそのまま所得税額から引かれる税額控除ではなく、課税の対象となる所得金額から引かれる所得控除であるという点には注意が必要です。また、対象となる医療費には制限がありますが、上述の健康保険や高額療養費制度では適用されない先進医療や自由診療の中にも医療費控除の対象となるものがあります。
まとめ
受ける医療や費用によって、公的医療保険制度が適用されるものと適用されないものがありますので、場合によっては自己負担が大きくなることも予想されます。そのような場合への備えとしては、貯蓄で賄うのか、民間の医療保険に加入するのかを考えることになるでしょう。そして、民間の医療保険への加入を検討するにあたっては、まず公的医療保険制度でカバーできる内容を理解したうえで、不足する部分を民間の医療保険で補う、と考えることが大切です。
- ※バックナンバーは、原則執筆当時の法令・税制等に基づいて書かれたものをそのまま掲載していますが、一部最新データ等に加筆修正しているものもあります。
- ※コラムニストは、その当時のFP広報センタースタッフであり、コラムは執筆者個人の見解で執筆したものです。